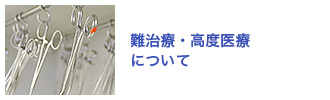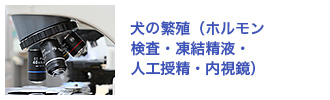カレンダー
最近のエントリー
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
トキソプラズマ症
10年06月29日
トキソプラズマToxoplasma gondiiという寄生虫を病原虫とする疾患で、人では猫から妊婦さんに感染すると流産や奇形、障害の原因となるといわれています。
トキソプラズマは成長した犬や猫が感染しても、免疫機構が正常であればほとんど症状を示しませんが、一部に不明熱を特徴とする元気消失、抑うつ状態、流産、中枢神経症状を示すことがあります。子犬や子猫では発熱、食欲不振、下痢、運動失調、痙攣、マヒなどの神経症状が現れ、重症化すると死亡することもあります。
診断は診特徴的な症状がないため、症状からは判断が困難です。糞便検査でトキソプラズマのオーシスト(卵の様なもの)を確認できれば確定診断ができます。
治療はサルファ剤、トリメトプリム、ピリタミンなどの投与によって行いますが、治癒・回復後は生涯にわたって宿主体内に潜伏し続けるという報告があります。
トキソプラズマは人には生肉や猫の糞を通して感染します。オーシストの排泄は多くの場合1歳未満の子猫で認められ、その期間は初感染後1~3週間くらいです。排泄されたオーシストは未熟な状態で、2~3日で成熟し感染力を持つようになります。「猫飼育+妊娠=トキソプラズマ症」という誤解がありますが、猫の糞便検査や抗体検査を行うなど感染状況を把握し、室内飼育の徹底や生肉を与えないようにすることで感染のリスクを下げることができます。特に拾った子猫の下痢などからオーシストが確認される機会が多いため、この場合は子猫の治療をすぐに開始することや、糞便処理には手袋などを用いてできるだけ早く処分することなどを心がけることが大切です。女性で不安がある方は内科や産婦人科を受診されることをお勧めいたします。
老齢犬の発作
10年06月23日
老齢犬の発作を主訴に来院される方は多く、日常診療の中でも関わる事が多い疾患です。
発作の原因は様々で、一般的には
・代謝性疾患(血液学的な異常である場合が多い)
・頭蓋内(つまり脳の)疾患
の大きく2つに分類されます。
原因次第で治療が全く異なる事から、必然的に検査項目は多くなってしまいますが、
印象としてはやはり高齢犬の場合は頭蓋内疾患である割合の方が高いと思います。
頭蓋内の疾患が強く疑われる場合、次にしなければならない検査はMRIとなります。
実際には「全身麻酔が必要」「非常に高価」等の問題もあり、ここまで臨めないケースも多いですが、
是非、比較的健康的な状態のうちに受けておきたいものです。
1度や2度の発作で命に危険が及ぶ事はあまり多くない様に感じますが、
この時点で原因を追究できれば、予後に大きな影響を及ぼす可能性があります。
上述の様に、時間がたち、状態が悪化すれば、もはや検査もできない
といった状況に陥りかねません
明らかな発作が起きた場合は、様子をみるのではなく、
なるべく早くご来院される事をお勧めいたします。
マラセチア皮膚炎
10年06月15日
マラセチア皮膚炎は、脂質好性無菌糸酵母菌(カビの仲間)であるMalassezia pachydermatisあるいは他のマラセチア種によって引き起こされる皮膚疾患です。マラセチア皮膚炎の病原性については未だ議論が続いていますが、過剰な皮脂分泌物や高い湿潤性および正常防御機構の崩壊がこの菌の増殖につながり、菌の生み出す酵素が炎症や痒みを引き起こすと考えられています。また、犬のマラセチア皮膚炎のほとんどがアレルギー性疾患や角化異常を伴う疾患および他の慢性あるいは再発性炎症性皮膚疾患が根底に存在することによって、二次的に起こると考えられています。
症状として、頚部腹側、腹部腹側、腋窩、顔面、耳介、四肢、全身の皺などに、痒みを伴う皮膚の赤み、脂っぽいフケ、脱毛などが認められ、慢性化すると皮膚がゾウの皮膚のように厚くなり、皮膚が黒っぽくなってきます。
好発犬種は、ウェスト・ハイランド・ホワイト・テリア、バセット・ハウンド、ジャーマン・シェパード・ドッグ、アメリカン・コッカー・スパニエル、シー・ズー、マルチーズ、チワワ、プードル、シェットランド・シープドッグ、ダックスフンド等です。
治療は、抗真菌剤の内服および抗真菌剤の添加されたシャンプーを用いてのシャンプー療法によって行われます。また前述の通り、マラセチア皮膚炎は他の疾患による皮膚のバリア機能低下によって二次的に起こると考えられているので、原疾患がはっきりしている場合はそちらに対する治療も行う必要があります。
これからしばらく暑い季節になり、皮膚のバリア機能も落ちやすい時期となりますが、定期的にシャンプーを行って、皮膚を清潔な状態に保つよう心掛けてあげてください。
犬のC反応性蛋白
10年06月08日
C反応性蛋白(CRP)は、当院でも、犬の炎症性疾患を疑ったときに検査する項目の1つであります。
生体に感染や組織傷害などのストレスが加わった際にこれに反応して短時間のの間に血中濃度が変動する一群の蛋白を急性期蛋白とよび、C反応性蛋白(CRP)は代表的な急性期蛋白です。主な産生臓器は、肝臓ですが、一部膵臓や、局所のリンパ球からも産生されるという報告があります。炎症性の刺激でよって、おもにマクロファージからサイトカインが産生されて肝細胞に作用します。もっとも重要なサイトカインはIL-6であり、肝細胞上のIL-6レセプターに結合し、CRPの産生が促されます。また、炎症性サイトカインは、内因性発熱物質でもありますので、発熱も引き起こされます。
CRPは、発見から70年以上たっていますが、生理的役割は未だ全て解明されていません。CRPは、細菌や真菌の細胞膜表面のリン脂質と結合します。また細胞が死亡(アポトーシス)すると細胞膜内のリン脂質が細胞外側に出てCRPと結合します。また、結合したCRPに補体や貪食細胞が結合し、貪食、殺菌効果がさらに促進されます。ヒトにおける研究では、CRPは刺激を受けてから、1日から2日で、血中濃度が数百倍から数千倍に上昇し、その半減期は、5〜7時間であります。CRPは、犬やヒトだけではなく、節足動物や軟骨魚まで存在が確認されていますが、炎症時におけるCRPの血中濃度の上昇の程度は種にとって大きく異なります。犬の炎症マーカーとして、CRPは有用でありますが、猫は、CRPは、健常時でも比較的高値を示し、炎症刺激に対する反応が鋭敏ではないため、炎症マーカーとしては不向きであるとされています。
現在犬の様々な疾病でのCRPの変化について報告がされておりまして、その有用性について、今後さらなる研究が期待されています。
肛門周囲腺腫
10年06月01日
肛門周囲腺から発生する腫瘍で、最も多いのは良性の腺腫です。この腫瘍は、アンドロゲンと呼ばれる雄性ホルモンに刺激されるため、未去勢の雄犬に多く見られます。雌犬で認められることもありますが、その場合、副腎から、テストステロンという雄性ホルモンが異常分泌されている可能性があります。
良性のものでも、痛み、掻痒感などからこすってしまうことによって潰瘍化することが多く、出血、炎症、感染を伴います。
未去勢の雄犬にできた腺腫は、その腫瘍自体を切除するだけではまた再発してしまうので、根本となるホルモン異常の原因を除去するために去勢を同時に行う事が必要となってきます。
未去勢の雄犬は高齢になるとホルモン異常によって会陰ヘルニアや前立腺肥大が多く見られます。
これらの疾病に対しては、去勢を行うことが予防になってきます。また、去勢手術をしない場合には、定期的なチェックや、よく気をつけてあげることが重要です。